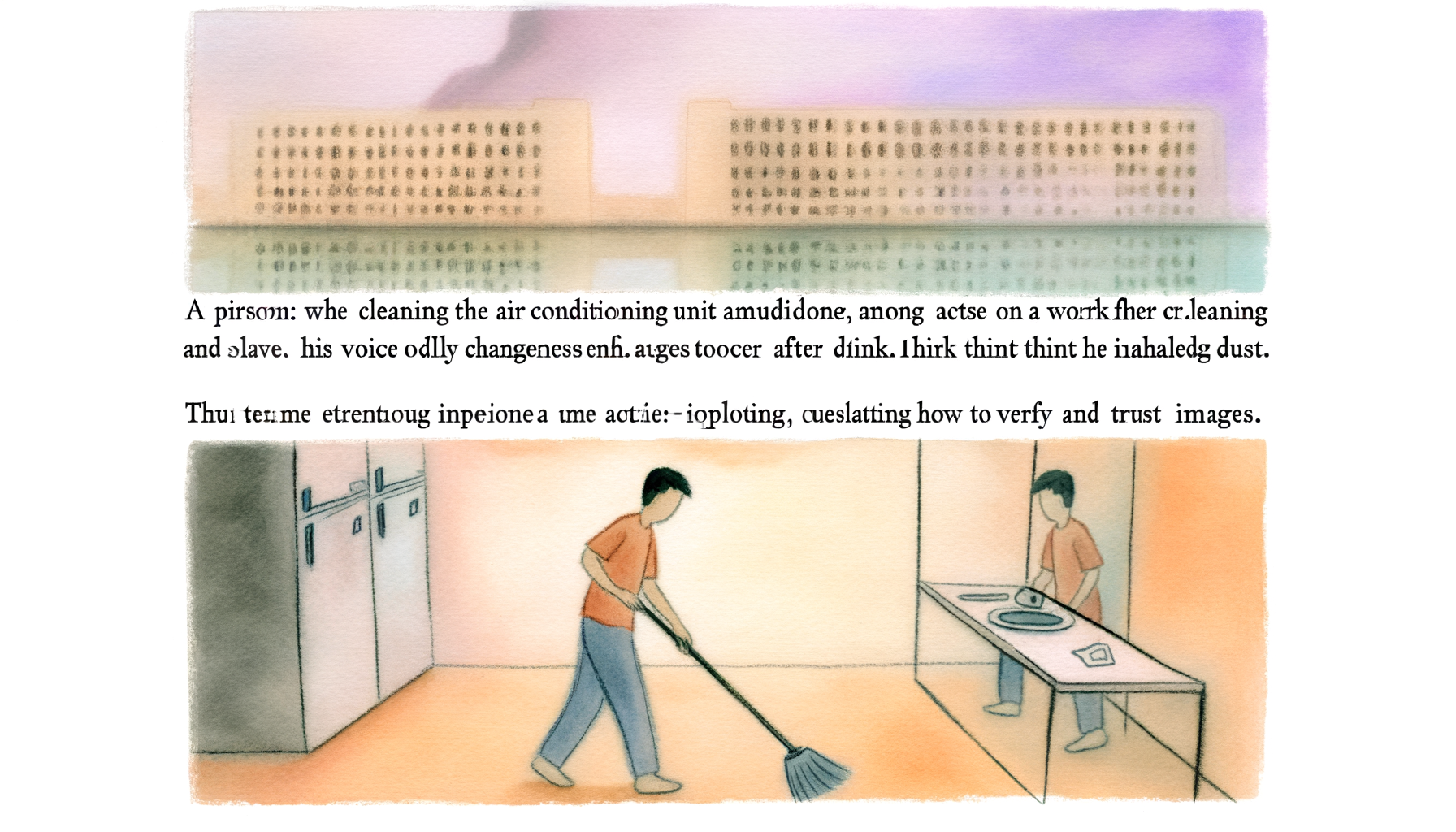2025年11月3日月曜日のニュースです。
子亀をくわえたタヌキの画像
報道があったのは昨日の夜で、日付としては一昨日の話になります。共同通信社が出した記事について、その中に付けられていた写真を取り消しました。鹿児島県の屋久島がウミガメの産卵地だということですが、ウミガメの専門施設が提供した画像が、生成AIで加工されたものだったという話です。
具体的に見ると、監視カメラで撮影された画像で、タヌキが小亀をくわえている写真があります。これをその施設の方が生成AIで加工した上で、共同通信に提供しました。その結果、共同通信として使用されることになったのです。共同通信は通信社であり、いろいろな新聞社が契約して運営されています。加盟社があって成り立っている通信社です。
共同通信に「この画像はAIで作られたのではないか」という指摘があったようで、共同通信側が調査した結果、加工された画像だと確認されました。共同通信の中では、生成AIを使用した画像を記事に使わないということが定められているようです。規約に抵触したために、画像を取り下げたというわけです。
記事として出ていた内容から判断すると、共同通信のチェックが不足していたことは間違いありません。ただし、共同通信が責任を問われるよりも、その生成AIによって見やすくするための加工が施されたというところに、施設側の落ち度があったことが大きいのではないかと思っています。
インターネット上では先日、共同通信のカメラマンが、高市政権に対して「支持率下げるぞ」という発言をし、それがネット配信に載って問題になったことがあります。
その影響から、「共同通信はまた印象操作をしたのではないか」というような意見がありますが、先ほどの経緯から考えると、私はそれが問題ではないと思います。
「AI加工してます?」とは聞かないのが当たり前だったのに…
確かにチェックが漏れていたのは事実ですが、画像を提供してもらう際に「何もAI加工されていませんか?」と確認することは、従来あらゆる媒体で、ほとんど行われていませんでした。
それによって、例えば取材相手の心証を損ね、協力してもらえなくなる可能性もありますし、相手方を信頼するという前提のもとに、しっかりした取材先だから安心して使用できると判断できる側面もあります。
しかし今回の件を機に、共同通信や各社は、AIによる加工があるかどうかを今後確認する必要が出てくるのではないかと思います。それでも、場合によっては、相手が「使っていない」と言ってくることもあるでしょう。
その時に、結果として誤報にならないように媒体側としてできることが何かというのは、非常に難しい問題です。
「論文チェックツール」も精度100%ではない現状
最近では、大学の論文などで、生成AIによって作成されたものかどうかをチェックするツールが導入されています。このツールを使うことで、「どれくらい人間らしいか」がわかるというものがあります。ただ、そこに精度が100%ということはもちろんなく、実際に自分で書いたものがAI判定された事例も報告されています。
したがって、これからは違和感に気づくかどうかが重要になってくるのではないかと思います。例えば、ChatGPTが生成する動画サービス「Sora」では、かなり高い精度で会話が作成されているわけですが、日本語の内容については、若干の違和感を感じることがあります。数ヶ月前に比べてかなり改善されてはいるものの、やはり注意が必要です。
「足で稼げ」とは言わないが、「もらい画像」の源流を探るのもメディアの仕事だ
今後、違和感を感じたときに、どう確認するのかという点も考慮が必要です。提供元への確認はもちろんですが、それでも疑いが晴れない場合にはどう対処するのか、こうした生成AIの倫理的な問題を再考するきっかけになると思います。メディア側の慣習として、提供されたものをチェックせずに掲載することの意義も改めて問われるでしょう。
「足で稼げ」と言われることが多いですが、取材によって自分で素材を作ることが全てとは限りません。他の人が作ったものを使う以上は、その素材がどのように作られてきたか、流れをしっかりチェックしておく必要があります。結果的に誤報に繋がる可能性があるため、メディア関係者はしっかりと考えていかなければならない問題です。
それではまた次回です。
(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)