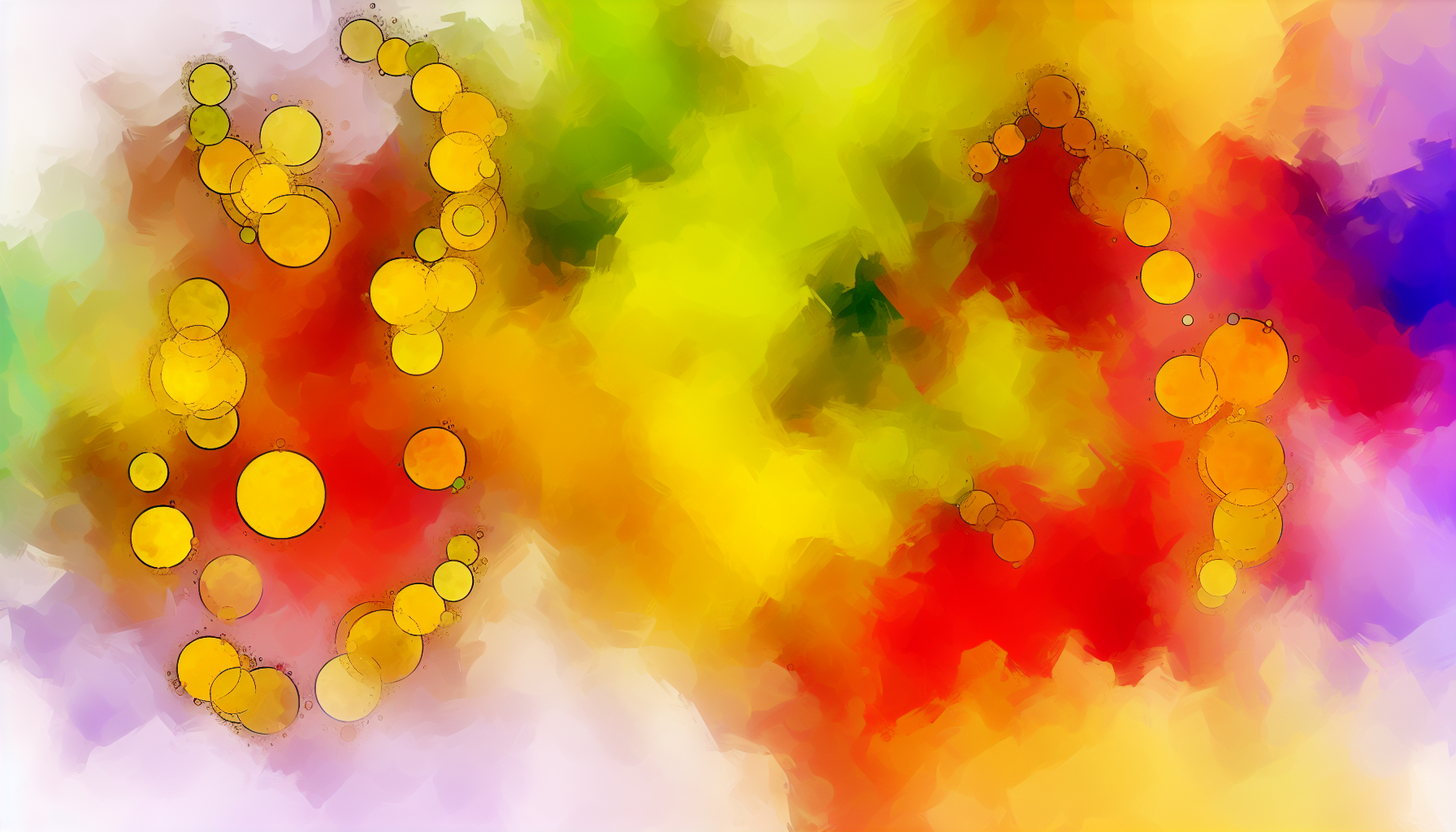2025年7月2日水曜日、のらニュースでございます。
健康保険料を見直している件
さて、ここ数日いろいろと動いておりまして、と言っても、まあ出かけているわけではないんですけど。先日、医療保険の話をしましたが、健康保険のほうがかなりお金が増えてしまって。ありがたいことに去年から今年にかけて結構仕事をいただけて、その結果が保険料にドーンと積み上がっているわけなんです。
さすがに表立って大きな額になってきているので、ちょっと見直して、文筆業が入れるような健康保険の組合を調べたりしています。また、そもそも、所得を減らせるようにいろんな控除が使えるように、経費の積み方をどうしようかなとか、そういったことも含めていろいろと調べて、動くところは動いてというのを今日はやっておりました。
本来やるべき仕事もあるんですけど、今日はちょっと仕事が楽な一日だったので、そうしていたわけなんですけれどもね。
有名実業家がメディア運営企業を買収
さて、本日の話題をご紹介します。7月に入ったということで、新たな動きが続出していますが、今日はですね、新たなメディアが生まれたという話をいくつかご紹介させていただこうと思います。1つはですね、堀江貴文さんたちとREAL VALUEという番組と会社をやっている溝口勇児さんがいらっしゃるんですが、彼はBreakingDownのCOOをされている方で、そういった界隈の方々に関わっているというイメージがあります。
この方が、NOBORDER(NoBorder)という、元々上杉隆さんというジャーナリストがやっていた会社を買収してCEOに就任したということが発表されました。具体的に何を行うかは今後公式なYouTubeチャンネルで伝えていくことになると思いますが、上杉隆さんはかつて自由報道協会という社団法人を作り、民主党政権の頃に記者会見を記者クラブではない形で開こうという活動をしていました。その後もいろいろとありましたので、そのあたりは皆さんお調べいただけたらと思います。一時は「NHKから国民を守る党」の副党首に就任されていたこともありました。
その会社を買収したというのは、なんとも面白い状況ですね。もう1つ、メディア関係の話題です。
元ロンブー淳さんも「経済メディア」立ち上げ
ロンドンブーツ1号2号を解散して元に戻った田村淳さんが、「XU(クロスユー)」という経済メディアを立ち上げると発表しました。昨日、淳さんが「明日僕の新しい挑戦を発表します」と言っていたので、政界進出の噂もあったのですが、ふたを開けてみると経済メディアの立ち上げということでした。運営する会社はHI-NEXU(ハイネクス)のようです。
プレスリリースによると、淳さんがエグゼクティブプロデューサーとして指揮を執る「次世代型ビジネスコミュニティメディア」であるXUは、「X innovation empowers U」の略だそう。今日、京都で開催されるイベントで正式にローンチする予定です。
「経済メディア」と淳さんを表現していますが、その中には業界や次世代をつなぐネットワークも盛り込まれているようなので、単に発信するだけではなくて、マッチング的な意味合いもあるのかなと感じます。
このように、コミュニティ要素が強めのメディアを立ち上げるということです。先ほどのNoBorderもそうですが、実際に動き出してみないとわからない部分があるので、今は発表されている内容でしか判断できません。
「タダ乗り」「文脈切り売り」への反発があるのでは
やはり、知名度のある方がメディアに乗り出すことはどういう意味があるのか、いろいろと考察したいと思います。もちろん、このお二方がそういう考えのもとではない可能性もありますので、あくまで私見として、あらゆる方が「メディアをやりたい」と感じる動機について、経験をもとに考えを述べます。
まず1つの背景として、「メディアへの不信感」が多少なりともあるのではないかと思います。特に、既存のマスメディアに出ている方にとっては、インターネットメディアに対する不信が強い部分があるかもしれません。
例えば、いわゆる「こたつ記事」の問題があって、マスメディアでコンテンツとして大きく取り上げられているものが、ただ乗りされて、切り売りされ、その文脈が損なわれることで本来の意図とは異なるものが伝わってしまう。そんな、もどかしさやいらだちから、自分でコントロールできるようなメディアを持ちたいという考えにつながっているのではないかと考えます。
知名度が上がるにつれ「情報のハブ」にもなる
次に、表に出る方々が一定の知名度やステータスを持つと、立場に見合った情報が集まるようになります。そうして集まった情報を、本業以外の部分で活かす機会がなかなかないというのはもったいないと思います。ビジネスパーソンであればメディアを運営しない限り、その集まった情報を有効活用するのが難しいように思います。
芸能人も同様で、発信力を持ち情報が集まっているにも関わらず、マスメディアでは公正なものであれ、「100%自分のやりたいこと」ができるわけではないという現実があります。自分自身がコンテンツを生み出す側に回りたいと思った時、デジタルのプラットフォームには非常に大きな価値があることに気づくことが多いです。
また、コロナ禍には「仕方なく」始めた方々も多かったと思います。ただ数年たって、その理由が変わりつつあり、いまや「自分が中心となりコンテンツを発信すること」に魅力を感じている人が増えていると感じます。
「一部のファンにめちゃくちゃウケる」コンテンツとの親和性
つまり、使い分けが大事です。マスメディアにはマスメディアの役割がありますが、それとは別の角度から、ネット、特にYouTube動画などで新たな表現ができるようになってきています。そして、例えば「ダウンタウンチャンネル(仮称)」のような動画中心のコミュニティも登場予定ですが、あれは「マスメディア」と「ネットメディア」の違い、そして感覚の違いを示していると思います。
マスメディアが「より多くの人に刺さる」ことを目的にする一方で、ネットメディアは「一部のファンにめちゃくちゃウケる」ことが特徴です。こうした状況において、自分のやりたいことができる場を求めるという傾向が、知名度のある方々の間で強まっているのではないかと感じています。
とはいえ、メディアを運営するためにはそれなりの資金も必要です。そのお金を使えるほどの経済的余裕があること、つまり、本業でそれなりの経済的な力量がなければ、運営はカツカツになってしまいます。メディアを運営する立場になれるのは、それなりの地位と名声、そして資金を持つ方々でないと難しいのが現実でしょう。
以上のような考察を交えつつ、今日、7月から始まるメディアについてご紹介いたしました。それではまた次回お会いしましょう。
(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)