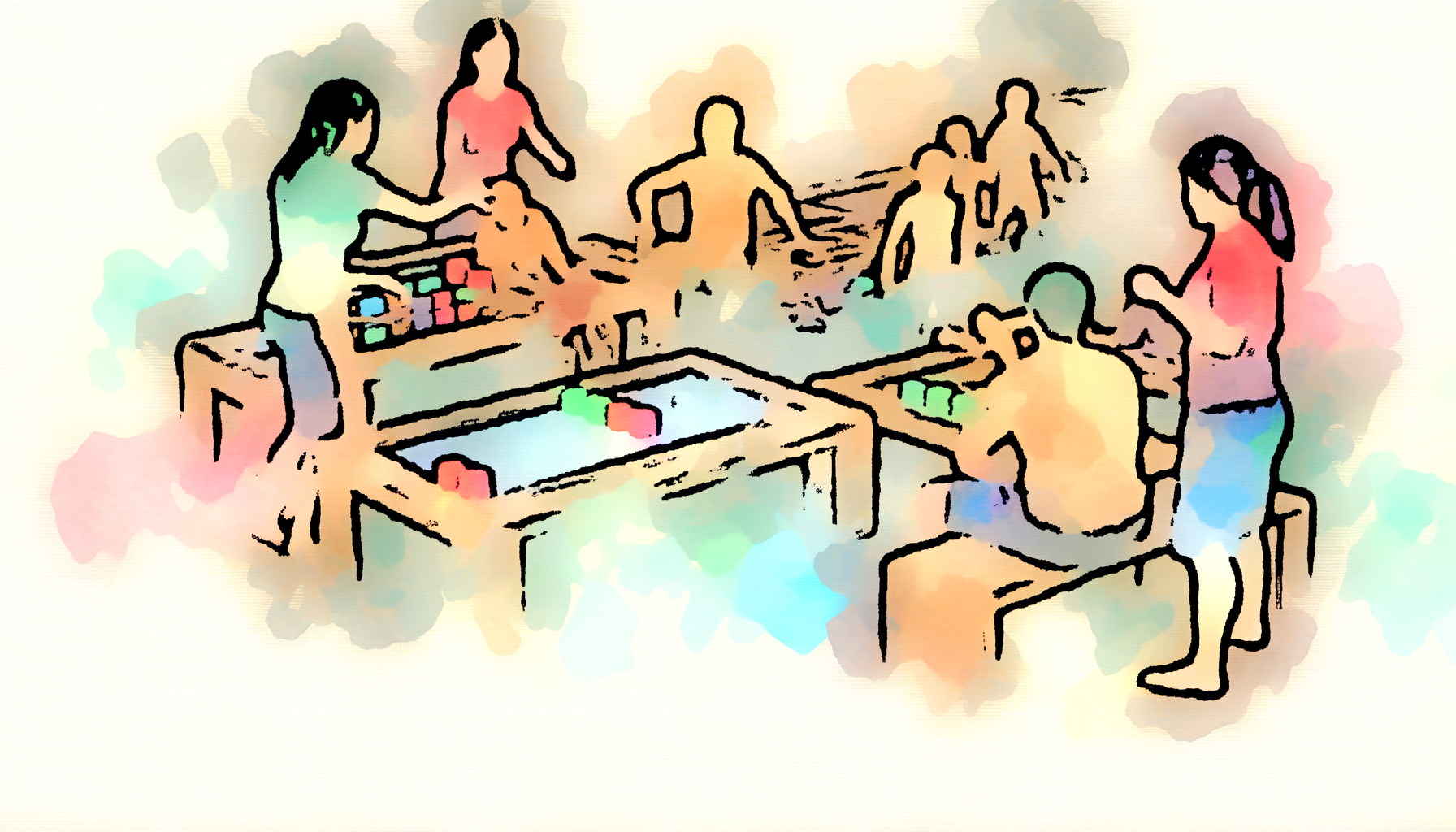2025年11月10日月曜日の「のらニュース」でございます。
「再生の道」初めての当選者が
大体、日曜日に選挙があって、翌月曜日に話題が盛り上がるという感じが多いのですが、東京都内では、葛飾区長選挙および葛飾区議会議員選挙が行われました。
特筆すべき点は、これは驚かなくなってしまったかもしれませんが、参政党がトップ当選したことや、石丸伸二さんが前代表を務めていた「再生の道」の所属者が初めて議会に当選したことですかね。
「再生の道」はこれまで、選挙には挑戦していたものの、当選された方はいらっしゃらなかったので、これは初めての事例となります。ここを皮切りに、都内各地での選挙に出てくるのかなとも思ったりしますが、今後の方針については奥村光貴・新代表が「AIペンギンさんに任せる」とおっしゃっていましたが、その浸透度がどのようになるかも気になりますよね。
伊東市長選と立花党首逮捕
今日は選挙絡みのお話をしますが、ここ最近、しばらく国政選挙がないと世の中が判断しているからでしょうか? 時代が動き始めていて、数日前にはNHK党の立花孝志党首が逮捕されたという報道もありました。逮捕理由は国外逃亡の恐れがあるということでしたが、その辺がどうなのかはわかりません。
静岡県伊東市の田久保真紀市長が失職となりました。立花氏がその選挙に出馬する意向を表明しているので、それがどうなるかも注目です。ただ、起訴されて、その後結審するまで、公民権の制限があるかというと、必ずしもそうではありません。実際に表には出られない状況でも、選挙には出られる可能性が高いと思います。つばさの党でも、過去に獄中から立候補した方がいましたしね。
現職と新人が「同じ票数」で確定
今日はその中でも茨城県の神栖市長選挙についてご紹介いたします。こちらはかなり報道されていますので、ご興味を持たれている方も多いと思います。現職の候補者と新人の候補者の一騎打ちで、現時点では新人の木内敏之さんが当選となっていますが、その経緯が非常に注目されています。現職の石田進さんと木内さんの両方が1万6724票という同数で確定したのです。
公職選挙法において同数の場合、くじ引きで当選者を決めることになっています。その結果、新人の木内さんの方が当選となったわけです。石田さんは票の数え直しが必要ではないかと異議申し立てを行っているようです。
無効票は219票存在していると発表されていますが、その無効票の判断基準はその場の選挙管理委員会によって変わるため、判断が難しい部分もあります。同数でここまでこじれるとは思っていなかったので、判断基準が変わる可能性もあるでしょう。正直に言うと、これは変わっちゃいけないんですけどね。
再集計によって状況は変わるのか
こんなに同数でくじ引きに持ち込むことは珍しいと思います。数票差でも異議申し立てがあったりすることはよくありますが、219票の差ではぎりぎりOKなのかもしれません。
ただ、石田さんが申立てたのですが、その票の中に、仮に「石田票と認められていたが、再確認により疑義がある」という票があれば、「もともと1票差で木内さんが勝っていた」という判断になる可能性もあります。非常にリスクの高い状況ですが、数え直しが行われるということです。
僅差で当落を決める要因として、「案分票」についてもお話ししたいです。たとえば「鈴木太郎さん」と「佐藤太郎さん」が同時に立候補した場合、「太郎」とだけ書いた場合には両者に票が入る仕組みがあります。こういうことも影響を与え、0.何票差で当落が決まることも珍しくありません。
僅差なら、なおさら「敗者の思い」を背負う必要がある
一騎打ちの区長選挙では、同数でくじ引きというのは少ないと思われます。ただ、最近では一騎打ちだけでなく、三つ巴や人数が多い選挙においても、上位2人が僅差で決まることが多い印象です。杉並区の区長選挙も3年前にあった際、現職と新人の候補者が100票台の差で、現職が落選しました。
これは「区政が変わってほしい」と思う人が多かったということですが、現状維持を希望する人々も半数いたことを示します。民主主義では、51対49の場合、51の方が勝つのですが、51を取った方は、残された49の思いも背負う必要があります。この意識を持って行動しなければなりません。
「明確な対立構図」が求められるご時世だからこそ…
選挙では対立構図を示した方が受かりやすい仕組みになっているため、過激なことを言って相手を煽ることが増えています。これは旧来メディアとネットメディアの対立構図とも関係しており、私自身は好みではありませんが、実際問題として、そのようなことが受け入れられている現状があります。そうなってくると、「明確な意見」を持つ2候補の間で、僅差で決まることが非常に多くなっています。
アメリカ大統領がバイデンさんからトランプさんになったように、明確な色を出していくことによって、政権ごとに国としての方向性が大きく変わるとなると、日本を含めた周辺各国はどうしていくのかがわからなくなります。
上院や下院の議員たちも、これだけ政策が変わるなら、自分たちの存在はどうなるのかと考えるかもしれません。勝った側はしっかりとコントロールしなければならないという側面がありますね。
対立構図のはざまにある「中間層」の重要性
政治家は、きっぱりした主張の間をどう埋めるかを考えなければなりません。ただ、当選だけが目的になってしまうと、色を明確にすることが有利に働きます。「市長派」と「反市長派」のような構図で考えられると、自分がわかりやすくなるため、そうした傾向に陥ることがあります。
中間層の無党派層の人々が、こんなに分かれている世の中でどちらに投票すればよいのかと考えると、やはり、「どちらも大事だ」というようなことを言える人を真ん中に立てる必要があります。過激な主張をする方々もいますが、必ずしも全ての意見がそのように極端であるわけではありません。
1年半後の統一地方選で「真ん中の人たち」が、どれだけ受かるか
統一地方選挙が再来年に行われますが、その時に極端な主張をする人たちがこれだけ知られている中で、どれだけ真ん中の人たちを浮かせられるかが、今後の民主主義日本の方向性を決定していくのではないかと思います。
選挙絡みのお話が長くなってしまいました。それではまた次回お会いしましょう。
(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)