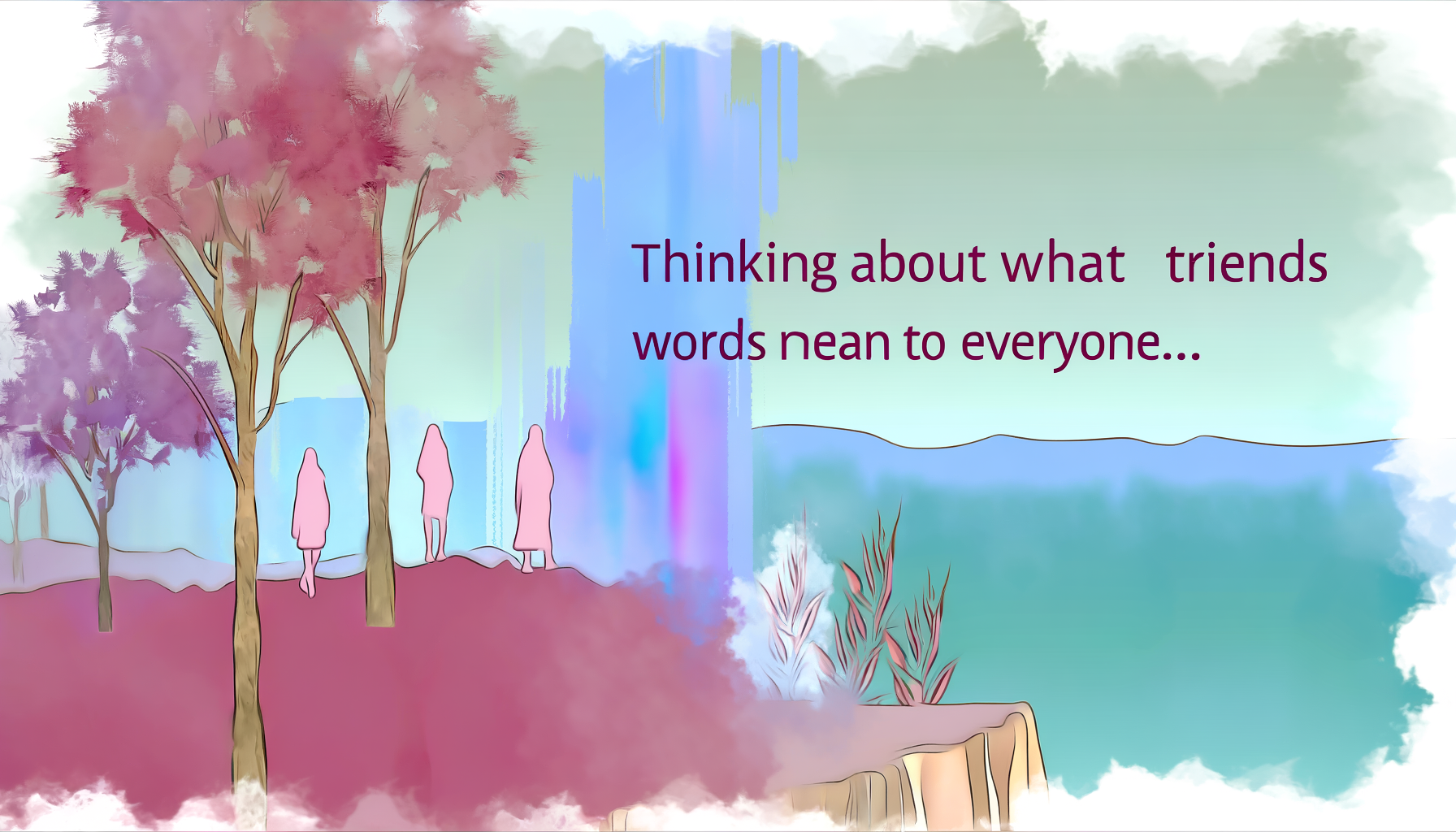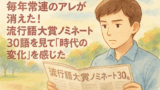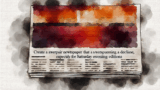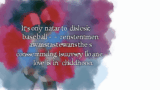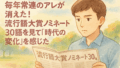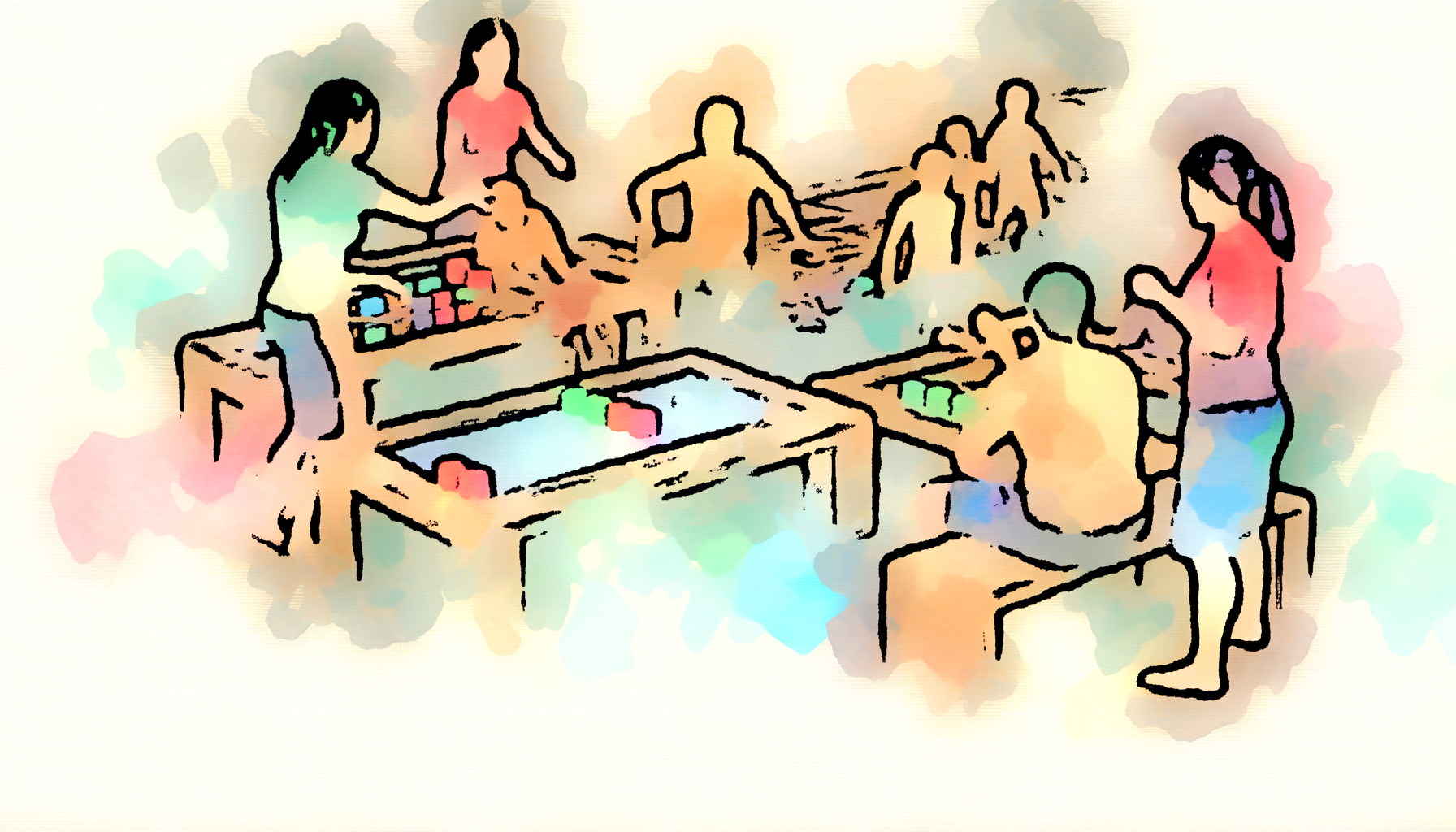2025年11月6日木曜日のらニュースでございます。
きのうのブログが結構読まれてる件
さて、昨日お話しした新語・流行語大賞のことですが、かなり注目されていたようで、ブログの方にたくさんのアクセスが来ております。ありがたいですね。やっぱり世の中で今、どういうことが起きているのかを追いかけるのが私の仕事なんですけれども。
普段、コラムとして書いて掲載先の媒体に載るときには、すごくわかりやすい形になっているんですが、自分のブログでそれをいろいろ見ていただけるのは本当にありがたいことですね。もうこの波が掴みにくくて、どうすればアクセス数が増えるのかと悩んでいます。
YouTubeも一応配信していますけれども、今のチャンネル登録者数は25人ということです。まだまだ弱小も弱小で、マネタイズは先の先という感じですね。その辺の自己ブランディングをどうしていくのかが、フリーランス4年目を迎えた私のこれからの課題かなと思ったりしています。流行語大賞やその時々の世相を反映するものは、すごく注目を集めがちだと感じています。
過去にこういうのが読まれたよ、って話
私の専門分野はどちらかというとネットニュースを中心としたメディア関係のお話が多いのですが、それも時たま注目を集めることがあります。例えば、新聞の夕刊について、最近土曜日の夕刊を休止する新聞社が相次いでいるということをまとめたところ、少し読まれましたね。
また、最近じわじわとアクセスが多いのは「野球ってどうなの?」という話です。私が子供の頃は、普通にナイター中継があって、9時24分くらいまで最大延長になることがありました。特に日本シリーズの日は、見たかった番組が中止になったり、遅い時間にずれ込むことがあって、誰しもが野球好きではないということを感じました。
我々世代のトラウマとして、見たい番組が野球中継によってなくなってしまったという思いがあります。むしろ、雨が降ってくれてよかったと感じることもありましたね。その頃はドーム球場が多くなかったので、運命的に中止になることもありました。東京ドームは私が生まれた年にできたので、あるところにはあったわけですけれども。
どうしても野球中継に対する嫌悪感から、野球そのものへの嫌悪感につながった人が一定数いると思います。その後、私が高校時代にライブドアが球団に参入しようとしたとき、当時の読売・渡邉恒雄主筆が、少し旧態依然とした村社会を意識させるような発言をしていたことから、そもそもプロ野球って何だろうかと反感を持った人が多いのではないかと思います。特にテレビ好きの人たちにはそのような人がいたのではないかと思います。
「ライター」というデカい主語による弊害
こうした Web ライティングの仕事を通じて体験したことを考えると、検索流入に対する対処法は少し私がこれまでやってきたインターネットニュースの世界とは異なると思います。よく「ライター論」という話がネット上でされることがありますが、ライターとなったら収入が本当に微々たるものでも発生するため、参入障壁が非常に低く、それだけプレイヤーも多いです。そのため、それぞれのライター同士での関係性には、いろいろとあったりします。
そうなると、その解像度を合わせないと、ギクシャクした話になることもあります。特に「Webライター」という大きなくくりにしてしまうと、主語が大きすぎて話が噛み合わなくなることが多々あります。私は基本的には、ネットニュースの仕事を通して、SNSからの流入もありますが、配信先、例えば YahooやLINEなどへの記事掲載の後、どのように読まれ、自社に戻ってくるかを意識して仕事をしています。
「検索エンジン対策」あまり実はしてこなかった
検索エンジンへの最適化、つまり SEO という表現があり、これは Search Engine Optimization の略です。この手法が注目されているのは、Google さまのご機嫌を伺うことが鍵になります。どうにかして検索の上位に引っかかるように、単語として人々が調べたくなるようなタイトルや内容にしなければなりません。
私は 「SEO ライター」としての知見はあまり持っていないのですが、記事を出して見出しも含めて、どのようにコンテンツとして届けるかを考えています。技術的な面について詳しくないとはいえ、やはり自分でブログを運営してみて、会社員時代にはメディア会社に所属していたこともあり、自分の言葉であれこれ話すことが炎上につながるリスクを考慮していました。
SNS も Facebook は極めてクローズドなものですし、会社員時代には会社に所属している自覚を持ちながら投稿することがほとんどでした。だからこそ、自分の気持ちを伝えることについて様々考えます。そこで、SEO に引っかかるノウハウと、自分が伝えたい想いとが本当に相性がいいものかを考えるわけです。
「検索で引っかかりやすい文章」と、「コラム的な文章」は全然違う
特にコラムやエッセイにおいては、文体がその人の性格や考え方を反映するものです。しかし、SEO的な書き方だと、例えば固有名詞を何度も繰り返すという技術が効果的だと言われますが、私はその手法はあまり好みません。同じ内容がだらだら続くのはくどいと感じ、ニュースメディアの編集者としては、同じ言い回しを避けるようにし、なるべくギュッと詰め込んで、伝えたいことを届けたいと思っています。
結果として、見出しの付け方も、できるだけインパクトのある言葉を入れることや、受ける言い回しが時代や媒体によって変化することを考えています。10年ほど同じ会社にいましたが、そこでのやり方と、今関わっているところのやり方は全然違っていますので、一から勉強し直しているところです。
環境に応じて、見せ方は変わる。だからこそ…
そうなると、やっぱり一概に何が適切かということは考えなければならないと感じています。ブログとコラムの違いや、YouTubeで声を喋って、それを文章化すること、さらに ChatGPT を使って文章化することと、文語の違いもあります。そうなると、スムーズに行えるように、一つのこの喋っているコンテンツを文章化する方法、そしてそれをどう届けるかも悩ましい問題です。
届けたい相手と、伝えたいこと、さらには収益化についても考えています。広告を貼ることには躊躇しませんが、果たしてそれが見てもらえるのか、最終的に私のライターとしての仕事や知名度が上がればいいと考えています。そのため、ブログそのものでお金を収益を得る必要がないのかなというスタンスがあります。
さまざまなことを考えつつ、私はミーハーでいたいと思っています。今日の話は少し適当になってしまいましたが、この辺で終わらせていただきます。それではまた次回です。
(以上はコラムニスト・城戸譲が、ポッドキャスト「のらニュース」などで話した内容を、AI文字起こし・要約によってブログ記事化したものです。公開時点で最新情報ではない可能性があるため、その点はご了承ください)